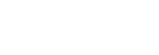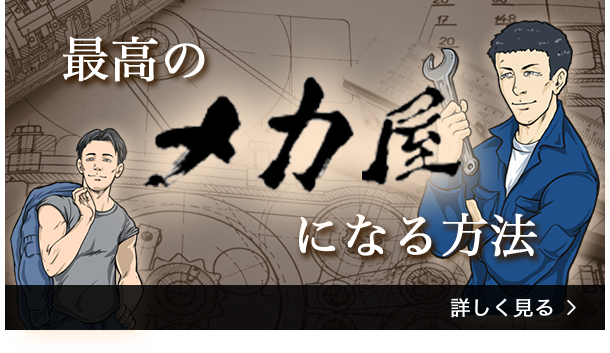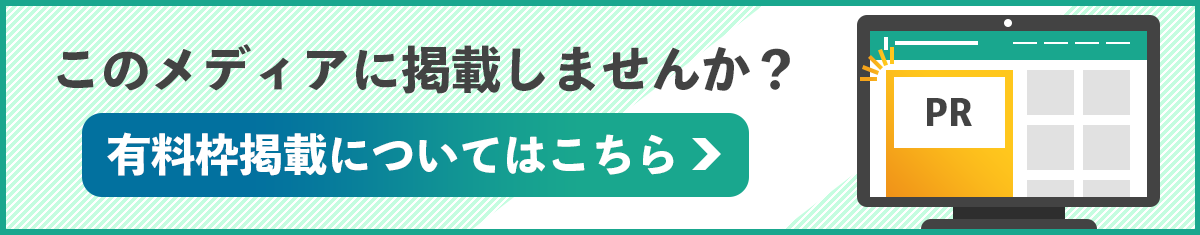機械設計エンジニアが勉強すべき機械力学とは
機械力学とはなにか?
機械力学とは、機械を作ったり運用したりする上で必要になる知識「4大力学」のうちのひとつ。簡単に言えば機械を働かせたとき、その動作によって生じる力について扱った学問のことです。
自動車や家電製品、ロボット、工場の生産ラインなど、身の回りのありとあらゆる機械の動作は全て機械力学に基づいて考えられているもの。機械設計エンジニアとして働く上でも重要な要素となります。
簡単なところからいけば、動いている機械には歯車やベルトなどに使用されているでしょう。これらの物体から伝わる力について、基礎的な知識を学ぶのが機械力学というわけです。
機械力学で主に扱われているのは、動く物体による力関係を扱う「動力学」と動かない物体に対して働きかける力を扱う「静力学」の2つ。機械力学では全ての物体が、力を加えても変化しない「剛体」であると考えられています。
少し難しいことのように聞こえますが、機械力学の内容は高校で習うような力学の延長線上にあるものです。学校で習った物理の内容が機械力学に相当しています。
なぜ機械力学がエンジニアに必要なのか?
機械設計のエンジニアとして、設計した機械がどのような動きをするのかを基礎から考える力が求められます。
例えば歯車がどのような力でどのような動きをするのか、ベルトに伝わる力がどのくらいのものなのか。機械の回転運動や往復運動、自動制御装置などを設計するにあたり、機械力学の考え方が基盤となってくるのです。
機械力学の基礎を正しく学んで身につけておかないと、機械設計に携わることはできませんし、そもそもエンジニアとして仕事をすることも難しいでしょう。例えば自動車などを設計する場合は、物体を回転させる機構を実現するために機械力学が用いられます。
重心の位置によるタイヤへの荷重を計算するにしても、機械力学を理解しておく必要があるでしょう。ほかにもエンジンの回転速度や加速度など、機械力学を通して考えられている機構ばかりです。
どんなモノづくりをするにしても、大前提は機械力学を理解していること。学校で学ぶ単純な内容ですが、エンジニアと機械力学は切っても切り離せないものと言えます。
機械力学の具体的な内容
実際に機械力学の考え方が利用されているのは自動車やロボット、エンジンなど。それらを設計するために用いられる機械力学は基礎的な内容を挙げると次のものがあります。
- ニュートンの運動3法則
- 力のつり合い
- てこの原理
- 重心
- トラス構造・ラーメン構造
- 摩擦力・摩擦係数
- 運動学
- 落下と放物運動
- 遠心力・向心力・慣性力
- 振動
- 固有振動数・共振・危険速度
慣性の法則やてこの原理などは、学生時代に習った記憶があるのではないでしょうか?こうした学生時代に学んだ物理の延長線上にあるのが機械力学の知識です。
作用・反作用の法則などは荷物を運ぶブルドーザーの動きなどに使われていて、遠心力の知識はボールを遠くへ飛ばすための野球バットを設計ときの参考に。トラス構造は橋やタワーといった建築物に、ラーメン構造は鉄筋コンクリートの建物などに利用されています。
身近な物がどのような機械力学に基づいたものかを理解していると、機械設計エンジニアとして設計や加工に役立てることができるでしょう。
メカ屋としての充実を
叶える方法を紹介!

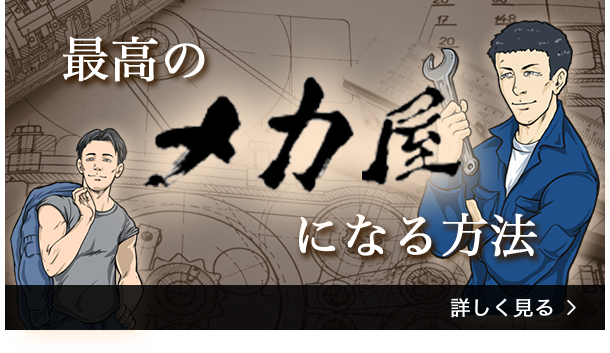
派遣のメカ屋を
目指す方はこちら