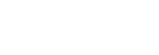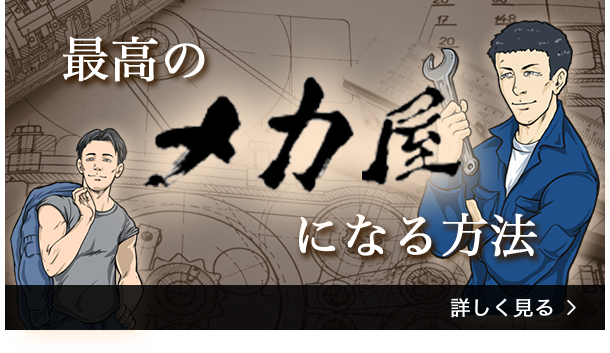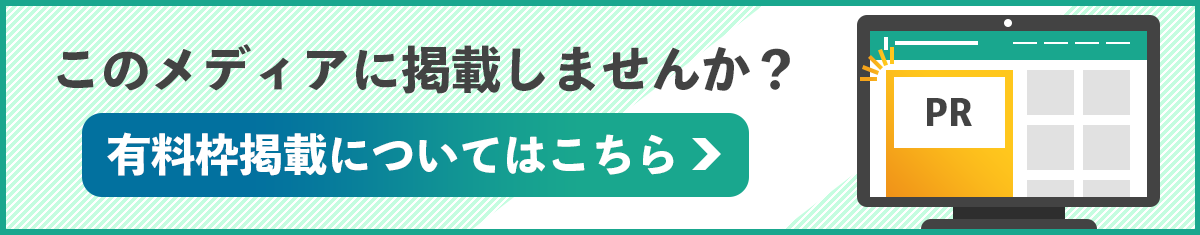材料力学が機械設計エンジニアに必要な理由
材料力学とは何か?
材料力学とは、機械設計のエンジニアが学ぶべき「4大力学」のうちのひとつ。機械を構成する材料について考えるのが材料力学と呼ばれるもので、機械設計をビジネスとして捉える場合は材料力学が利益を大きく左右します。
どんな機械でも、それを構成するために数々の部品が使われていることでしょう。この部品たちが期待に応えられるだけの動きをして、壊れず使い続けられる程度に設計するのが材料力学の考え方です。
熱力学や流体力学、機械力学に基づいて、機械を設計するのにどれだけの材料が必要になるのかを考えるのが、材料力学の役割。機械を使用する間に部品が変形しないか?壊れないか?不安定にならないか?といった点について調査をして、緻密に設計・計算します。
他の力学と違って、材料力学は機械そのものを動かしたり機能を実現したりするためのものではありません。一見地味な印象がありますが、材料力学に基づいた設計がないと機械は満足に動かないところでしょう。いわば縁の下の力持ち、機械設計をする上で最も重要な土台づくりを担うパートが材料力学です。
なぜ材料力学がエンジニアに必要なのか?
機械設計のエンジニアに求められるのは、最も品質の良い機械を、最も低いコストで実現させるための設計をすること。材料力学はこの目的を果たす重要な根幹部分。
機械が壊れず安定して長く使い続けられるよう、かつ経済的と言える範囲内のコストで材料費を抑えられるよう、計算や調査をしながら微調整をするのが材料力学の役割です。
例えば低コストで設計しようと材料費を削った場合、材料が足りないせいで強度が脆くなり、すぐに壊れるような機械ができてしまいます。これでは当然商品が売れません。商品生産の工場ラインに採用することもできないでしょう。
同じように、今度は品質を重視して壊れにくい安定した機械を設計したとしても、材料費が予算をオーバーしてしまっては利益が出ません。これらの品質とコストのバランスを計算しながら、最も「ちょうど良い」と言えるラインを見極めるために材料力学が使われています。
いわば材料力学を極めている機械設計エンジニアなら、経済的で高品質な設計が期待できるということ。製造コストやランニングコストを削減したがる企業は多くあるでしょう。そのため材料力学に精通したエンジニアが歓迎されやすいのです。
材料力学の具体的な内容
材料力学として学ぶ具体的な内容は、物体に働きかける力関係がメインとなります。
- SI単位系
- 応力
- ひずみ
- 引張強度・許容応力・安全率
- 材料の曲げに対する強さ
- たわみ量計算
- せん断応力
- クリープと疲労による破壊
- 熱応力
- 座屈
材料力学のメインとなる「応力」は単位面積あたりにかかる力のこと。応力が大きくなればなるほど部品が破損しやすくなるということを理解したうえで、機械設計に役立てられています。
材料がどのくらいの力で曲がったりたわんだりするのか、切断されるのか…。部品や材料に加わる力関係についての知識をつけることで、品質と経済性を兼ね備えた機械設計ができるようになるのです。
<PR>デジタルマイクロスコープを "観つける"【デジ観る】
メカ屋としての充実を
叶える方法を紹介!

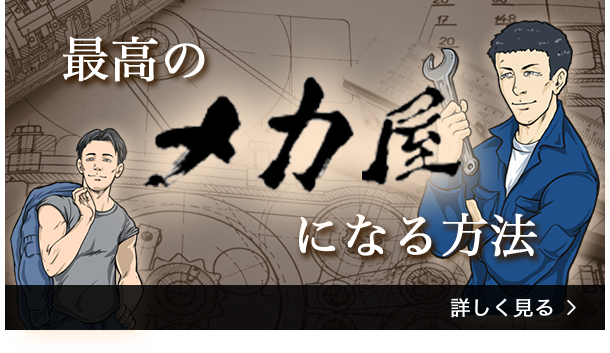
派遣のメカ屋を
目指す方はこちら